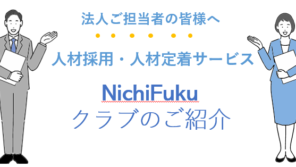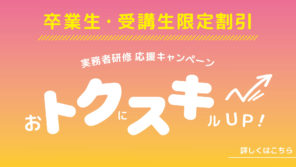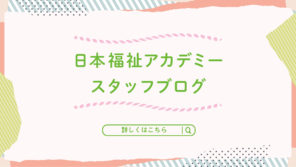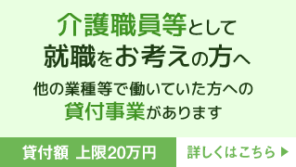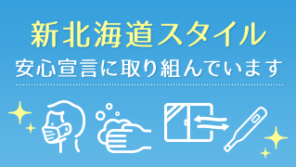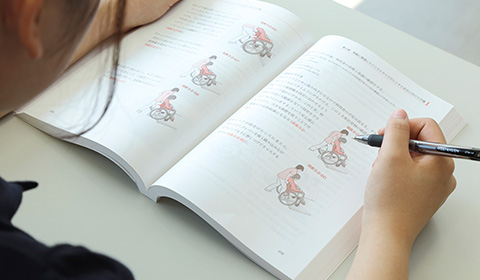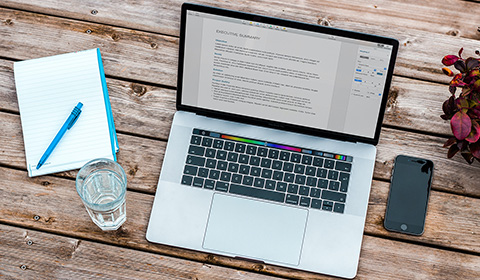新着情報
News
-
2024.05.02
-
2024.04.22
-
2024.04.16
講座案内
一人ひとりの
ステップアップをサポート!
スキルアップや資格取得を、
それぞれのペースに合わせて
経験豊富な講師陣がサポートします。
選ばれる理由
選ばれるには理由がある!
知識・技術だけではなく、
「おもてなし心」を持った介護業界の
担い手の
スキルアップや資格取得を、
経験豊富な講師陣が支えます!
未来の福祉を支える、
KAIGOの担い手を
育てます。

地域密着型の学校だからこそできる
人材確保と人材育成のサポート事業所のお客様へ
日本福祉アカデミーは、介護士の育成に貢献するため、多くの介護事業所様とお取引をさせて頂いております。
事業所様のニーズに合わせて、オーダーメイドの研修や人材採用と定着を目的とした法人様向けサービスをご用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。